マーボー豆腐のMサイズをテイクアウトで。(ストロー付)
2007年11月9日 その他
彼女の中では「マーボー豆腐」ってそういう存在ってことですかね。「マーボー豆腐は飲み物です。」のタイトルで一躍有名になった若槻千夏のブログを書籍化したものです。まぁ、私は彼女のブログはそんなに読んでないんですけどね。でも、ふと考えたんだけど、なんで今こんなに「ブログ人気」なんでしょう?自分もやっているくせにいうのもなんですが。
私も含めてのことなんですが、なんだかんだいっても、「誰かに読んで欲しい。」という部分はあるからだと思うんですが、現在ではブログって新旧で2種類あるように思うんですよね。つまり、もともと「ブログ」と呼ばれていたものは、海外で生まれ、個人形情報発信のツールとして誕生したわけですが、日本に上陸するにあたって、「日記のようなもの」と紹介されたことで、新しいブログが出来てきたと思うんです。
で、その新しいブログというのが、携帯で自分の日常の瞬間を切り取るもの。これを究極の形にしたのが中川翔子だと思うんです。実は最近でこそぜんぜん読んでませんけど、彼女が「1日に何回更新できるか」ということだけにこだわっていた頃、ちょっと衝撃を受けたんですよね。よくても私は1日に1回書くものって思ってたんですが、彼女の場合は10の位で更新していく。写真になんか一言付け加えてすぐ更新というスタイルは、「ブログをこんな風に使うヤツがいるのか!」って、その柔軟な頭脳に感服したもんです。
で、この若槻さんのなんですけど、これまたそういう系統でもないように思うんですよね。なんかうまく言えないけど、自分のことをさらけだして書くという部分でいうと、「痛々しい」というか「辛そう」な感じ?がするんですよねぇ・・・私だけかなぁ?自分の目に写るものだけを信じて、その中から「答え」らしきものをずっと探し歩いているような・・・おっさんの経験からいうと、それは蜃気楼を追いかけるようなもので、実際の「答えらしきもの」はすぐ足元にあることも少なくないのに。
今の若い子って驚くほど大人びているよねぇ・・・。いろんなことを考えて思い悩んだりもするし、そういう時間ももちろん大切だと思うけど、多くの人に出会っているうちに自分のこともわかってくるという、「急がばまわれ」みたいなことって案外あるからねぇ・・・。若槻さんのブログが人気なのも、何か魅力があるからだと思うけど、このままだと息切れしそうな気がするのは気のせいかな?まぁ、ここも4年目でそういう感じはなくはないですけどね。(苦笑)ともさかりえさんのブログにあるように、私も「ボチボチ」行こうとは思っているんですけど。
※書籍のトリビア
本を出版したら(原則自費除く)必ず、流通前に「ISBN」という番号がふられます。同時にこれは国立国会図書館が全ての出版物を永久に蔵書することを意味します。この「マーボー豆腐〜」ももちろん文献資料として1冊は確かに保管されます。これは国立国会図書館が「全ての図書館の図書館」であるからです。100年後の今日になると、この本は当時の世相を探る文献資料として利用されるかも?
私も含めてのことなんですが、なんだかんだいっても、「誰かに読んで欲しい。」という部分はあるからだと思うんですが、現在ではブログって新旧で2種類あるように思うんですよね。つまり、もともと「ブログ」と呼ばれていたものは、海外で生まれ、個人形情報発信のツールとして誕生したわけですが、日本に上陸するにあたって、「日記のようなもの」と紹介されたことで、新しいブログが出来てきたと思うんです。
で、その新しいブログというのが、携帯で自分の日常の瞬間を切り取るもの。これを究極の形にしたのが中川翔子だと思うんです。実は最近でこそぜんぜん読んでませんけど、彼女が「1日に何回更新できるか」ということだけにこだわっていた頃、ちょっと衝撃を受けたんですよね。よくても私は1日に1回書くものって思ってたんですが、彼女の場合は10の位で更新していく。写真になんか一言付け加えてすぐ更新というスタイルは、「ブログをこんな風に使うヤツがいるのか!」って、その柔軟な頭脳に感服したもんです。
で、この若槻さんのなんですけど、これまたそういう系統でもないように思うんですよね。なんかうまく言えないけど、自分のことをさらけだして書くという部分でいうと、「痛々しい」というか「辛そう」な感じ?がするんですよねぇ・・・私だけかなぁ?自分の目に写るものだけを信じて、その中から「答え」らしきものをずっと探し歩いているような・・・おっさんの経験からいうと、それは蜃気楼を追いかけるようなもので、実際の「答えらしきもの」はすぐ足元にあることも少なくないのに。
今の若い子って驚くほど大人びているよねぇ・・・。いろんなことを考えて思い悩んだりもするし、そういう時間ももちろん大切だと思うけど、多くの人に出会っているうちに自分のこともわかってくるという、「急がばまわれ」みたいなことって案外あるからねぇ・・・。若槻さんのブログが人気なのも、何か魅力があるからだと思うけど、このままだと息切れしそうな気がするのは気のせいかな?まぁ、ここも4年目でそういう感じはなくはないですけどね。(苦笑)ともさかりえさんのブログにあるように、私も「ボチボチ」行こうとは思っているんですけど。
※書籍のトリビア
本を出版したら(原則自費除く)必ず、流通前に「ISBN」という番号がふられます。同時にこれは国立国会図書館が全ての出版物を永久に蔵書することを意味します。この「マーボー豆腐〜」ももちろん文献資料として1冊は確かに保管されます。これは国立国会図書館が「全ての図書館の図書館」であるからです。100年後の今日になると、この本は当時の世相を探る文献資料として利用されるかも?

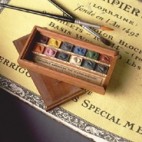
コメント